目 子どもの病気 教えて!ドクター
眼は物を見るために非常に複雑な、しかも合理的な仕組みで出来ています。人の感覚器では、最も精細な道具といえましょう。それは、光を受け取る眼球と、その情報を脳の視中枢に伝える視路と、眼球を保護したり、動かしたりする付属器からなっています。眼球は図1のようになっています。
光はまず角膜から眼内に入り、瞳孔→水晶体→硝子体を通り、そして網膜(カメラではフィルム)に外界の映像を映すのです。その映像は視路を伝って脳の中枢で認識されます。その途中で障害があれば、例えば角膜や水晶体が濁っていればよい視力が得られないのです。
子どもの眼球は、生まれた時は直径17~18㎜くらいの大きさで、5、6歳になると大人に近い22~23㎜の大きさに発育します。ところが、生まれたときは、すでに相当の大きさである子どもの眼ですが、視力は、明暗か、せいぜい眼の前で手を振るのがわかる程度で、正に未熟なのです。
しかし、子どもの眼は、物を見る学習を適切に行えば、未熟な視力も5、6歳になれば、大人と変わらない視力1.0から1.2に発達をしているのです。
この未熟な視力の発達すべき条件は
①適切なパターン刺激(形のある映像)が両眼内へ入る。
②両眼網膜の中央に同時に投影する。
③その映像が網膜にピントが合っている。が必要な条件です。
0歳から5、6歳までの視覚発達の大切な時期にこれらの件に合わないものとして、①は生まれつきの片眼の白内障や眼瞼下垂や、最も重要な2歳までの片眼帯などで起こる遮断弱視があります。
②については、眼の向きが両眼同時に目標に向いていない斜視は、斜視眼は不使用で斜視弱視となりやすく、交代性の斜視ならば、弱視とならなくても両眼視機能の不全になることが多いのです。
③は非常に症例は多く、屈折異常で、ある程度以上の強さの遠視や乱視で起こりやすいのです。両眼性では屈折異常性弱視、片眼の度が特に強いために起こる不同視弱視があります。
※弱視とは、屈折異常をレンズで矯正しても視力が出にくいものをいいます。その点では近視は裸眼視力がよくなくとも、矯正視力が出るので、弱視とは言いません。

正視とは、無限遠から眼内に取り入れられた光は、主として角膜と水晶体で屈折され、ちょうど網膜に焦点が合うものを言います。焦点が合わないものを屈折異常といいます。なお、調節は緩めた状態で定義します。角膜と水晶体が、ちょうど眼軸長に合致してよく見えるのが正視です。図1のようになります。

遠視とは、眼の屈折力が網膜に焦点を合わすには弱くて、焦点が網膜の後方にいってしまうもので、子どもでは先天性に遠視であることが多く、ある程度以上の遠視は、弱視や斜視になりやすく、はやく眼鏡で矯正してやらねばなりません。
近視とは、眼の屈折力が強すぎて、焦点が網膜の手前に結ぶので、遠見は見にくいのですが、近見は比較的見やすく、しかも後天性であることが多く、弱視にはなりにくいのです。
乱視とは、子どもでは、主に角膜の表面が正しい球面でなく、縦方向と横方向のカーブが異なるため、ピントの合う位置が違うので、明瞭に見えません。そこで先天性の強い乱視は弱視になりやすいのです。
不同視とは、屈折異常の種類をいうのではなく、左右の眼の屈折の種類や度が異なるものをいいます。左右差が大きいと、度の強い方が弱視になりやすいので、片眼の弱視すなわち不同視弱視となってしまいます。そこで早期にメガネをかけるだけでなく、弱視眼をしっかり使わせるため、よい方の眼を抑えるため、健眼をアイパッチで遮閉する治療が必要です。
どのような病気でもそうですが、早期発見が、子どもの視力発達をチェックするのに最も必要な対策です。有難いことは、わが国では、1990年から、従来から施行されていた「3歳児健康診査」に視力検査が取り上げられるようになりました。おおむね、子どもは3歳を過ぎると視力検査が可能となりますので、これは、正に貴重な機会です。ここで、屈折異常の疑いや、弱視を起こす可能性のある屈折異常を発見すれば、早速に眼科の先生に受診されることをお勧めします。
さらに、視力検査ができなくとも、斜視は見かけで発見できますし、また、家庭でも目つきや、日常の物を見る仕草を注意していれば、視力低下を家庭で発見することは可能なのです。
子どもの視力を守るには、6歳では、遅すぎるのです。
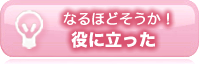

4人
3人

Copyright © 2011 Mikihouse child & family research and marketing institute inc. All rights reserved.